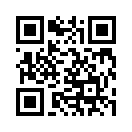1997年09月07日
深夜放送考
深夜放送というジャンルがかつてラジオというメディアに存在した時代があった。
ニッポン放送のオールナイトニッポン、TBSのパックイン・ミュージック、それから文化放送のセイ・ヤング。私の青春時代もそれら深夜放送とほぼ共生する形で成立した。そんな時代があったのだ。パーソナリティーがいて、全国からのリスナーから寄せられる葉書を読み、見ず知らずの常連たちの顔、形を想像させ、生放送という「共有時間」に孤独をまぎらわせた。
良き時代だった。中学生、高校生といった最も感性のとがった聴取層を相手にすれば、一時の言い逃れのような嘘は、すぐに見破られる。つまり、ジョッキーは「演じる」ことの不可能に行き当たる。「キャラクター」は否定され「パーソナル」が信頼された時代の話だ。だがテレビ番組の進出や、その他の娯楽の発展に押されるように、こういったラジオを通じての互いの「パーソナル」の対決といった面倒は見捨てられ、一過性の熱病に近い「ブーム」は他に持ち去られ、ラジオは、一時、メディアの主流の座を追われた。
以来、ムーブメントはテレビが主導権を握ることとなるわけだが、奇妙なことに、それと、軌を一にして、青春たちが、己で考えることをおろそかにし始めた(気がする)。一方的に甘受する知識の断片を、ただ、観ることによってあたかも己の知識欲が満たされることになり、結果、甘受することに慣れ切ってしまった。
もちろんラジオが正しくテレビが間違っているなどという馬鹿化た極論を吐く気はないが、少なくともラジオというメディアは、見えない分、人々の右脳に働き掛け、想像力を育てたことは確かだ。人は、本能として聞くことよりも見ることを信頼しやすい。ダイアナ元妃の亊故死(?)という悲報に接し、もしかしたら、人の死のシーンの多さが、人に、生命の重さを軽んじさせてはいないか、という不安。きょうもテレビドラマでたくさんの人が死んでゆく。「見せる」もマインドコントロールの一つ。
良き時代だった。中学生、高校生といった最も感性のとがった聴取層を相手にすれば、一時の言い逃れのような嘘は、すぐに見破られる。つまり、ジョッキーは「演じる」ことの不可能に行き当たる。「キャラクター」は否定され「パーソナル」が信頼された時代の話だ。だがテレビ番組の進出や、その他の娯楽の発展に押されるように、こういったラジオを通じての互いの「パーソナル」の対決といった面倒は見捨てられ、一過性の熱病に近い「ブーム」は他に持ち去られ、ラジオは、一時、メディアの主流の座を追われた。
以来、ムーブメントはテレビが主導権を握ることとなるわけだが、奇妙なことに、それと、軌を一にして、青春たちが、己で考えることをおろそかにし始めた(気がする)。一方的に甘受する知識の断片を、ただ、観ることによってあたかも己の知識欲が満たされることになり、結果、甘受することに慣れ切ってしまった。
もちろんラジオが正しくテレビが間違っているなどという馬鹿化た極論を吐く気はないが、少なくともラジオというメディアは、見えない分、人々の右脳に働き掛け、想像力を育てたことは確かだ。人は、本能として聞くことよりも見ることを信頼しやすい。ダイアナ元妃の亊故死(?)という悲報に接し、もしかしたら、人の死のシーンの多さが、人に、生命の重さを軽んじさせてはいないか、という不安。きょうもテレビドラマでたくさんの人が死んでゆく。「見せる」もマインドコントロールの一つ。
Posted by たおまさ at 03:58