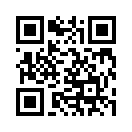2007年03月16日
幻獣について
「幻獣」とは、ボクの愛読書のひとつ「日本幻獣図説」の著者、湯本豪一氏らが語る「生物のカテゴリー」で、これを強く支持します。
現在、一般的に、「幽霊」と「妖怪」は明らかに違うモノのカテゴリーとして定着しています。ヒュ〜ドロドロと出てくる半透明みたいな煙みたいなのが「幽霊」で、ヌラリヒョンや座敷童子、一反木綿みたいな、ゲゲゲの某に出てくるのが「妖怪」であります。では「幻獣」とは何か。
例えば、河童や人魚や鬼。大雑把な分類ではおそらく「妖怪」にカテゴライズされてしまう彼らは、一反木綿とは明らかに違う一面があります。それは、ひょっとしたら生物として実在しているかもしれない、と古来思われてきた点です。その証拠に、日本各地で目撃談や接触談が民間伝承として残り、遺物が残されていたりします。彼らが出現したという当時の新聞記事が残されていたりもします。日本人は古来から、実際には出会ったことの無い、どこか不可思議な存在である河童や鬼に、明らかにリアルに「生」を感じていたのであり、イマドキでいう未確認生命体、いわゆるUMAに近い存在だといえます。そんな彼らを「妖怪」と区別しようというのが「幻獣」というカテゴリです。逆に、座敷童子などの妖怪は「気配」を想像で具体化した存在だといえるでしょう。
科学が発達した今、存在が完全に否定される「幻獣」も当然います。逆に、マンボウやカモノハシは江戸時代の文献では「幻獣」扱いでした。そしてニホンオオカミなどは、昔は普通に存在したのに今や「幻獣」となってしまったといえるかもしれません。
湯本氏は本の中で、国内の代表的な幻獣として、河童、鬼、天狗、人魚、龍、雷獣を挙げています。そしてちょっと調べてみると、どうやら彼らは和歌山県内にも存在した、いや生息した足跡を密やかに残しているようなのです。科学的な観点から、彼らの存在を否定することは容易いでしょう。しかしボクは、この和歌山の深い山奥に、清流の底深くに、岸から離れた無人島に、ひょっとしたら彼らは本当にいるんじゃなかろうかと思っていた文化に、とてつもない奥深さとロマンを感じてやまないのです。
現在、一般的に、「幽霊」と「妖怪」は明らかに違うモノのカテゴリーとして定着しています。ヒュ〜ドロドロと出てくる半透明みたいな煙みたいなのが「幽霊」で、ヌラリヒョンや座敷童子、一反木綿みたいな、ゲゲゲの某に出てくるのが「妖怪」であります。では「幻獣」とは何か。
例えば、河童や人魚や鬼。大雑把な分類ではおそらく「妖怪」にカテゴライズされてしまう彼らは、一反木綿とは明らかに違う一面があります。それは、ひょっとしたら生物として実在しているかもしれない、と古来思われてきた点です。その証拠に、日本各地で目撃談や接触談が民間伝承として残り、遺物が残されていたりします。彼らが出現したという当時の新聞記事が残されていたりもします。日本人は古来から、実際には出会ったことの無い、どこか不可思議な存在である河童や鬼に、明らかにリアルに「生」を感じていたのであり、イマドキでいう未確認生命体、いわゆるUMAに近い存在だといえます。そんな彼らを「妖怪」と区別しようというのが「幻獣」というカテゴリです。逆に、座敷童子などの妖怪は「気配」を想像で具体化した存在だといえるでしょう。
科学が発達した今、存在が完全に否定される「幻獣」も当然います。逆に、マンボウやカモノハシは江戸時代の文献では「幻獣」扱いでした。そしてニホンオオカミなどは、昔は普通に存在したのに今や「幻獣」となってしまったといえるかもしれません。
湯本氏は本の中で、国内の代表的な幻獣として、河童、鬼、天狗、人魚、龍、雷獣を挙げています。そしてちょっと調べてみると、どうやら彼らは和歌山県内にも存在した、いや生息した足跡を密やかに残しているようなのです。科学的な観点から、彼らの存在を否定することは容易いでしょう。しかしボクは、この和歌山の深い山奥に、清流の底深くに、岸から離れた無人島に、ひょっとしたら彼らは本当にいるんじゃなかろうかと思っていた文化に、とてつもない奥深さとロマンを感じてやまないのです。
| 日本幻獣図説 | |
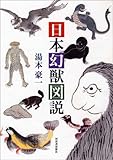 | 湯本 豪一 河出書房新社 2005-07-21 売り上げランキング : 385799 Amazonで詳しく見る |
Posted by たおまさ at 06:06│Comments(0)
│Mono